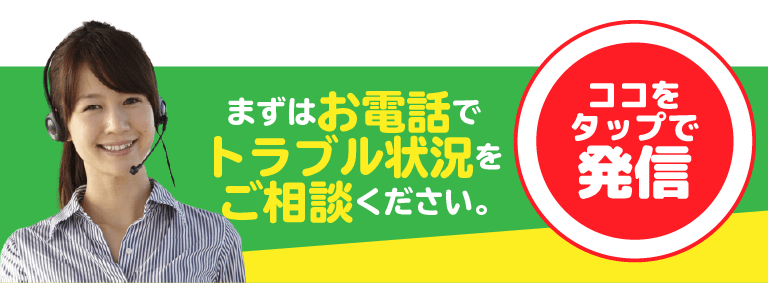水道管の凍結に注意するように呼びかけられていても、関東に住んでいると、「さすがにこの地域では凍結しないだろう」とつい安易に考えてしまいがちですよね。しかし、実際には関東での水道管凍結の被害も報告されており、さらに寒冷地域と比べて対策が疎かになりがちな関東では、凍結時の被害も大きくなりやすい傾向にあります。そのため、雪が降らないような地域や比較的温暖な関東地域に住んでいても、冬場の水道管凍結には注意が必要なのです。そこで今回の記事では、関東でも水道管が凍結する原因や放置した際のリスク、そして自宅でできる水道管凍結の予防法を詳しく解説していきます。冬本番を迎える前にぜひチェックしておきましょう。
関東でも水道管が凍結する理由とは?

一般的に関東地方は比較的温暖な気候とされていますが、実際には冬の冷え込みが厳しい地域も多く、水道管の凍結は決して他人事ではありません。特に寒波の影響で一時的に気温が氷点下まで下がると、普段は問題のない住宅でも凍結が起きることがあります。ここでは、関東でも水道管が凍結してしまう主な理由を見ていきましょう。
外気にさらされた配管が多い
関東の住宅は、北海道や東北のような寒冷地仕様で設計されていないケースがほとんどです。そのため、屋外の蛇口やベランダ、外壁沿いの配管などが露出したままになっていることが多く、冷たい外気に直接触れる状態になっています。特に夜間や早朝は放射冷却現象によって気温が急激に下がり、気温が氷点下に達すると、管の内部にある水が凍って膨張し、詰まりや破損を引き起こします。外気温がわずかマイナス1〜2℃でも、金属製の管は熱伝導率が高いため、内部まで冷え切ってしまうのです。
寒暖差の大きい地域もある
関東では日中は10℃以上あっても、夜間には氷点下近くまで下がる「寒暖差の激しい気候」が特徴の地域もあります。具体的には埼玉県北部や群馬県南部、栃木県南部などの地域が該当します。夜間に急激な温度変化があると、水道管の金属部分に負担をかけ、内部の水温を一気に下げてしまいます。また、冬型の気圧配置になると北風が強く吹きつけ、風の当たる北側の壁やベランダの配管ほど冷え込みやすい傾向があります。特に、日当たりの悪い場所や建物の陰になっている部分では、昼間でも気温が上がりにくく、凍結の危険性が高まります。
断熱対策が不十分な住宅が多い
関東の住宅では、寒冷地と異なり「凍結を前提とした設計」が行われていないことが多く見られます。築年数が古い住宅ほど、水道管を覆う保温材が劣化していたり、そもそも設置されていなかったりするケースも少なくありません。さらに、最近の住宅はデザイン重視で外観をすっきり見せるため、配管を外壁の表面近くに通すこともあり、冷気の影響を受けやすい構造になっています。断熱材が薄い外壁や床下部分では、冷気が内部に伝わりやすく、屋内にある給水管でも凍結することがあるのです。
長時間の留守や夜間に水を使わない
数日間の旅行や帰省などで家を空けている間、水道管内の水が動かない状態が続くと、冷気の影響を受けやすくなります。通常、水が流れていれば摩擦や流動によって温度が一定に保たれやすいのですが、静止している水は一晩の冷え込みでも凍ってしまうことがあります。寒冷地では凍結の危険がある時期には、あえて水道を開けっ放しにして水を動かし、凍結をしないようにしています。しかし関東地域ではこうした対策が取られないことが多く、結果として凍結被害に遭ってしまうのです。特に、夜間に水をまったく使わない家庭では、明け方の冷え込みによって屋外配管が凍りつくケースが多く、給湯器や蛇口に異常が出ることもあります。
地域特有の地形と気象条件
関東と一口に言っても、地域によって気象条件は大きく異なります。たとえば内陸部の群馬県南部や埼玉県北部、栃木県南部では、冬の放射冷却によって朝の最低気温が氷点下5℃近くまで下がる日も珍しくありません。逆に沿岸部の千葉や神奈川でも、強い寒波が流れ込むと短時間で冷え込み、凍結被害が発生します。都市部では建物が密集しているため気温が下がりにくいと言われますが、風の通り道となるビル街や屋上配管などでは冷却が進みやすく、意外な場所で凍結が起きることもあります。
水道管が凍結するとどうなる?

水道管が凍結すると、ただ水が出なくなるだけでは済まない場合があります。凍結は管内の水が氷に変わる現象ですが、氷は水よりも体積が大きくなるため、管内部に強い圧力がかかります。この圧力によって水道管が破裂したり、接続部分から水漏れが起こったりすることがあるのです。また、凍結は見た目にはわかりませんが、内部の水が膨張して管や蛇口の破損、さらには床や壁への水漏れなど二次被害を引き起こすリスクもあります。ここでは、凍結がもたらす具体的な被害について詳しく解説していきます。
水が使えなくなる
凍結が起こると、最初に気づくのは「水が使えない」という生活上の不便です。料理や洗濯、入浴だけでなく、トイレの水も使えなくなり、日常生活が大きく制限されます。特に冬場は暖房や給湯器も水を使うため、凍結による断水は生活のあらゆる面に影響します。また、外出中や夜間に凍結が発生すると、気づいたときには家の中で水が使えず、復旧までの時間が長くかかる場合もあります。さらに、小さな子どもや高齢者がいる家庭では、生活インフラが止まることによる健康リスクも無視できません。
膨張による破裂・漏水のリスクがある
水道管内の水が凍ると、氷の膨張で管に大きな圧力がかかります。これにより金属管や塩ビ管の破裂、接続部からの水漏れが起こることがあります。破裂が発生すると、噴き出した水が床や壁を濡らし、家財にも被害を及ぼす可能性があります。特に築年数が古い住宅や断熱の不十分な家では、管の破損による水漏れが建物の構造材にまで影響し、腐食やカビの発生を招きやすくなります。一度破裂が起こると、その後の修理費用が高額になるだけでなく、冬場の生活に大きな支障を与えることになります。
二次被害の可能性がある
水道管が凍結したまま放置すると、氷が解けた瞬間に大量の水が流れ出し、家屋内部で二次被害を引き起こすことがあります。壁や床の木材や断熱材が水分を吸収すると、腐食やカビの原因となり、室内環境の悪化や健康被害につながることもあります。さらに、浸水によって家電製品や家具が濡れて故障したり、修繕費用が想定以上にかかるケースも少なくありません。特に築年数の古い住宅では、凍結による水の膨張で目に見えないひび割れが起きており、次の冬に再度凍結被害が出やすくなることもあります。
配管設備の劣化や故障につながる
凍結による膨張や破裂は、給湯器や蛇口、分岐管などの周辺設備にも負荷をかけます。微細なひび割れや接続部分のゆるみが発生すると、水漏れや故障の原因となることがあります。さらに、凍結が一度でも起きた管は、内部に小さな亀裂が残ることが多く、次の冬にはより凍結しやすくなる「負の連鎖」に陥ることもあります。また、給湯器やポンプなどの関連設備も凍結の影響を受け、修理や交換が必要になるケースがあり、凍結被害は見た目以上に住宅全体の維持管理に影響を及ぼすのです。
水道管の凍結を防ぐための具体的な対策方法とは?

冬の寒さが本格化する前に、水道管の凍結を防ぐための対策を勉強しておくことは、安心して生活するためにとても大切なことです。しかし、まだまだ関東では聞き馴染がない「凍結」という言葉、実際にどのように対策すればいいか分からないという方も少なくありません。そこでここでは、今日から実践できる水道管凍結予防の具体的な方法を詳しく解説していきます。
配管に保温材を巻く
屋外に露出している配管や床下の管には、専用の保温材を巻くことが非常に効果的です。保温材には発泡ポリエチレン製のチューブや保温テープなどがあり、管に直接巻き付けることで冷気の影響を緩和できます。特に北側や日陰にある配管は冷え込みやすく、夜間の放射冷却で凍結するリスクが高い場所です。給湯器周りや分岐管など複雑な形状の配管も、専用カバーやチューブを活用して丁寧に保護することで、凍結の可能性を大幅に減らせます。さらに、断熱材を二重に巻いたり、風当たりの強い場所には保温材と防風シートを併用したりすると、さらに効果的です。
蛇口を少し開けて水を流す
水道管の凍結リスクが高い夜間や外出中には、室内の蛇口をわずかに開けて水を流しておく方法があります。水がゆっくり流れることで、管内の水温が下がりにくくなり、凍結を防ぐ効果があります。特に長い屋外配管や北側の配管は凍結しやすいため、水を少量流し続けておく方法は非常に有効です。少量の水でも循環することで、管内の水が凍りにくくなります。さらに、給湯管や分岐管など複数箇所で同時に少し水を流しておくと、住宅全体の凍結リスクをより低く抑えられます。
長期不在時の管理を徹底する
冬場に数日間以上家を空ける場合は、特別な対策が必要です。給湯管や屋外配管に水を残したままにせず、止水栓を閉めたり、配管内の水を抜いたりすることで凍結を防ぐことができます。また、暖房を最低限稼働させて室内温度を一定に保つことも有効です。特に古い住宅や断熱が不十分な家では、長期不在時に凍結が発生しやすくなるため、事前にしっかりと対策しておくことが安心につながります。さらに、外出中でも水抜き栓や保温材の装着状態を確認しておくと、帰宅後の凍結トラブルを防げます。
屋内の温度を一定に保つ
配管が通っている室内や床下の温度を安定させることも、凍結防止に効果的です。寒波の際に室温が極端に下がると、配管に近い水が凍りやすくなります。暖房や断熱材を活用して室温を一定に保つことで、屋内配管の凍結リスクを大幅に下げられます。また、床下や収納内は風通しが悪く冷えやすいため、小型ヒーターや断熱材で局所的に保温することも有効です。特に水道管が屋内外の境目を通る場合は、両側からの冷え込みに注意することが重要です。
給湯器や屋外蛇口の凍結防止機能を活用する
最新の給湯器には、冬場の凍結防止機能が標準搭載されている製品があります。温水を循環させる機能やヒーター内蔵の仕組みにより、水道管や給湯管が凍らないよう自動で温めてくれるのです。また、屋外蛇口にも凍結防止用カバーやヒーター付き製品があります。特に北側や風当たりの強い場所にある配管は、こうした製品を活用することで簡単に凍結リスクを減らせます。ヒーター付きカバーは、屋外でも安全に使用できる設計になっており、電源を入れておくだけで管内の水温を適切に保ってくれます。
◎合わせて読みたい記事!
給湯器の凍結予防を忘れずに! 慣れない凍結予防もこれで完ぺき!
https://www.elife-suidou.com/2024/02/09/10999/
まとめ
弊社では水回りトラブルの無料お見積り、修理を行っておりますのでお困りの際は是非ご連絡ください。関東エリア・東北エリア・東海エリア・関西エリアの各拠点にスタッフが待機しておりますので、お問い合わせから最短20分で駆けつけます。不安なことがありましたら是非ご連絡ください。