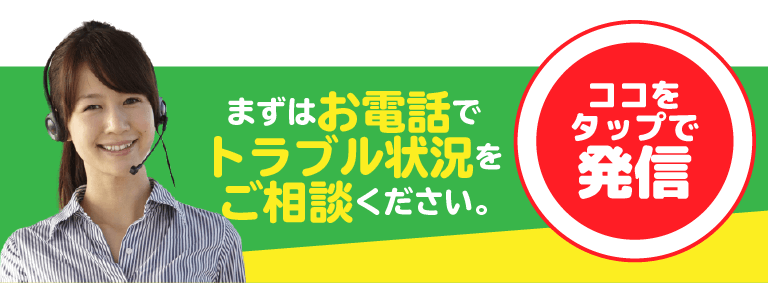暖かい日も増え、徐々に暖房の出番が少なくなりつつありますよね。夏に向かってどんどん暖かくなり、徐々に暖房から冷房の割合が増えていきます。日当たりがいいお部屋などでは既に室内温度が高く、日中はエアコンの冷房を使うという方もいらっしゃるのではないでしょうか。しかし冷房を使おうと久々にエアコンを付けたら「なんだかカビ臭い」「変な臭いが吹き出してきた」、エアコンに対してそんな風に感じたことはありませんか? 実はエアコンを使っていない季節の変わり目などに、エアコンのお手入れをしておかないとカビがどんどん繁殖してしまう原因になります。またエアコンの嫌な臭いの原因はほとんどがカビです。季節の変わり目にある今、エアコンのお手入れには最適な時期です。夏に困ることのないように、エアコンのお手入れをしっかりしておきましょう。今回はそんなエアコンのやっかいなカビの掃除方法や予防方法について、詳しく解説をしていきます。これから進学や転勤などで一人暮らしをするという方も増えるかと思いますが、エアコンのお手入れは健康管理の面でもとても大切ですので、是非覚えておいてくださいね。
エアコンにカビが繁殖する原因とは?

エアコンの内部でカビが発生してしまうこと自体は、そんなに珍しいものではありません。カビの度合いは違えど一度は経験があるという方も多いのではないでしょうか。エアコンの内部は普通に使っているだけでもカビが繁殖しやすい環境が整っているため、家の中でもカビが繁殖しやすい場所でもあります。では一体なぜエアコンの中にはカビが繁殖してしまうのでしょうか。エアコンの中にカビが繁殖してしまう原因について、一緒に見ていきましょう。
カビが活動しやすい室温になるため
エアコンを使用するような部屋は常に人がいることが多く、季節に応じて部屋の温度を調整しているという方は多いかとおもいます。カビは20度~30度程度の室温を好むと言われておりますが、同様に一年を通して人が適温だと感じる温度に近い部分があります。具体的には冬は20~23度程度、夏は25~28度程度の室温に調整している方が多く、人が適温だと感じる温度がカビの活動しやすい温度と重なっていることが分かるかと思います。そのため人が快適だと感じる室温はカビにも快適な室温になり、エアコン内部で繁殖が進んでしまう原因になります。
湿度が高くなりやすいため
カビは湿度が高い場所を好む傾向があります。エアコンは特に冷房使用時は内部で結露などが生じやすく、湿度が高い状態になりやすいです。そのためエアコン内部では、ジメジメした高湿度の環境が作られやすくカビが発生しやすくなってしまいます。結露が生じてしまうのはエアコン内部の断熱材が足りていないなどの可能性が考えられ、断熱材を増やすことで解決することが多いです。しかし結露に気付かずに使っているという方も少なくないため、気付いたらカビが発生していたというケースはよくあります。その他にカビの生じやすい場所としては、お風呂場があります。お風呂場のような高温多湿になりやすい環境は、特にカビが好む傾向があります。お風呂場は湿度が高くジメジメした空間になりやすいですが、そうした環境がエアコン内部で発生していると考えるとエアコン内部の環境がイメージしやすいかもしれません。
汚れが溜まりやすいため
エアコンの内部は風が出入りしているだけに見えて一見清潔に見えますが、実は室内のホコリや汚れなどを一緒に吸い込んでしまっているため、何もしていないとエアコン内部は汚れが蓄積されていきます。そうした汚れや結露による水垢汚れなどを養分として、カビは更に繁殖範囲を広げていってしまいます。カビが汚れや水垢を養分としていることを知らないという方も多いのですが、自宅でのカビの発生はこうした積み重ねが原因になることも多いです。
使用後すぐに電源を切ることで湿気が残るため
冷房や除湿を使ったあとのエアコン内部には、大量の湿気が残っています。冷たい空気を作る際には、熱交換器に結露が発生するため、内部はまるで濡れたタオルのような状態です。この状態で電源を切ってしまうと、湿気が逃げ場を失い、機器の内部にとどまってしまいます。特に気温と湿度が高い夏場は、エアコン内部がカビの繁殖にとって理想的な環境となります。カビは湿度70%以上・温度20~30℃程度で活発に繁殖するため、冷房停止直後のエアコン内部はまさに最適な「住処」になってしまうのです。
長期間エアコンを使わずカビが繁殖するため
季節によってエアコンを使わなくなる時期がありますが、その間、まったく掃除や点検をせずに放置しておくと、内部でカビが静かに繁殖してしまうことがあります。特に梅雨時期や秋口など、気温が高く湿度もある時期に使わないで放っておくと、エアコン内部の湿気が乾かず、カビにとって快適な環境が維持されてしまいます。また、フィルターや熱交換器に残ったホコリや汚れがエサとなり、カビの増殖を助けてしまいます。使用していない間に内部でカビがどんどん増えてしまい、いざ次のシーズンに使用した際に、カビ臭が部屋中に広がってしまうというトラブルに繋がるのです。
エアコンのカビを掃除する方法はある?

カビができてしまっても、長期間放置をしていない場合は自宅での対処ができるケースもあります。掃除中はほこりが舞うことが多いですので、マスクを装着した上で換気をしながら行うと、室内がほこりっぽくならずに済みます。また作業を始める前には必ずエアコンの電源を抜いてから行うようにしましょう。それではさっそく、エアコンのカビ掃除の方法について解説していきます。
フィルターの掃除方法
エアコンのカバーを上に押し上げるようにして外すと、中にホコリ取りのフィルターが一番最初に確認できるかと思います。フィルターは取り外しができますので、まずはフィルターを取り外し、床などの安全な場所に起きます。最初は掃除機を使用しながらフィルターについたホコリを取り除いていきます。ホコリはできる限りきれいに取り除いておいた方が、この後の作業がスムーズです。フィルターのホコリ取りが完了したら、次は水に濡らして絞った雑巾でフィルターを拭いていきます。これできれいに汚れが取れていれば問題ありませんが、ホコリが細かくびっしりついていてきれいに取り除けなかった、という場合は水洗いをしましょう。水洗いは洗面所などで水をフィルター後ろ側から流しかけていきます。この際に汚れがダマになっているなどの場合は、掃除用スポンジでこすりながら落としていきましょう。カビがしつこい場合には、中性洗剤を水に薄めたものをスポンジに吸い込ませ、フィルターを壊さない程度の力でこすり洗いし、最後に水で流しましょう。ここまで完了させたらフィルターの掃除は一通り終わりです。最後はできれば日光に当ててしっかり乾燥させてから、フィルターを戻しましょう。
吹き出し口の掃除方法
エアコン下部には吹き出し口が付いていますが、カビの繁殖が広がってしまっている場合、この吹き出し口部分にカビがこびりついてしまっていることがあります。エアコン吹き出し口のカビは見た目で気付くことが多いですが、しっかり取り除かないと部屋にカビが拡散されてしまうため注意が必要です。吹き出し口は脚立などを使用して作業することになるかと思いますが、可能であれば二人体制で安全を確保しながら進めましょう。脚立にのぼったら、最初にハタキなどを使ってホコリを取り除いていきます。次に雑巾で拭き作業をしていきますが、カビがついてしまっている場合は濡れた水だけでは逆に悪化させてしまうこともあります。そのため中性洗剤をしようしましょう。中性洗剤は水で薄め、雑巾に吸い込ませてから使うようにしましょう。洗剤の量が多すぎると泡だらけになってしまったり、エアコンの故障の原因にもなりますので、使用する量は少量で問題ありません。吹き出し口のカビをしっかりとこすり落とし、その後に水のみで濡らした雑巾で中性洗剤を拭き取っていきます。洗剤が残らないよう、手で吹き出し口を触った時にヌルヌルしていないか、なども確認しながら作業を進めていきましょう。洗剤をしっかり拭き取ることができたら、吹き出し口の掃除は完了です。
フィンの掃除方法
エアコンの心臓部分でもあるフィンは、熱交換機などとも呼ばれており、温度調整をする上で重要な部分です。エアコンのフィルターを外した奥に見える黒い機械がフィンです。これは業者でないと解体が難しい部分ですので、自宅でのお掃除では解体はしません。その代わりに掃除機を用いてホコリを吸い取り、全体的な汚れを取り除いていきます。フィンの掃除はここまでが自宅でできる範囲です。最後に取り外していたフィルターを取り付けて、エアコンの掃除は完了です。フィン専用掃除スプレーなども市販には販売してありますが、スプレーのかけ方などによっては故障の原因になることもあるため、自宅での積極的な使用はあまりオススメできない部分もあります。もし使う場合にはエアコンのメーカーに直接使っても問題ないか、また使う際の注意はあるかなどを確認しておくと安心です。
エアコン掃除をプロの業者に頼むべきケースとは?

自宅でエアコンのカビ取り掃除をする方法について解説をしてきましたが、実は上記の掃除方法を定期的に行っていたとしても、エアコンの内部を完全にきれいに保つことは難しいです。そのため以下の内容に当てはまるという方は、一度プロの業者に見てもらうようにしましょう。また作業を進めていたけれど自力では難しい、と感じた方も無理せず業者に依頼するようにしましょう。
長年カビを放置している
カビは一度発生してしまうと完全に取り除くことが難しいと言われているくらい、やっかいな存在です。そんなカビを年単位で放置してしまっているという方は、自宅にある洗剤などでは既に太刀打ちできない可能性もあります。また無理にとろうとして中途半端に剥がれたカビが、エアコン稼働時に部屋中に放出されてしまうという可能性もあります。こうした場合は最初からプロの業者に依頼し、プロの業者が使う洗浄剤などでしっかりきれいにしてもらうようにしましょう。
フィンにカビが付着している
フィンは取り外すことが可能な部品ではありますが、取り外すのが難しくデリケートな部品でもあるため扱い方にも注意が必要です。そのためフィンにカビが付着してしまった場合は、業者に来てもらいフィンを取り外して洗浄してもらうようにしましょう。外から見ると単純に見えてもエアコン内部はさまざまな部品や機械が入っているため、慣れていない方が無理に取り外そうとしてしまうと、故障の原因にもつながります。また綿棒などで掃除をしようとされる方も多いですが、フィンについてしまったカビは取り外して洗浄しない限りは完全に取り除くことができません。カビの繁殖をこれ以上広げないためにも、早い段階で業者に依頼してカビを取り除いてもらうようにしましょう。
業者に依頼してから1~2年が経過している
プロの業者によるエアコンのクリーニングは、年に1~2回推奨されています。そのため、前回業者に依頼してから期間が空いているという方は、再度業者に依頼して掃除をしてもらうようにすると安心です。もちろん普段の掃除も大切ですが、普段の掃除では取り除けない深い部分の掃除を業者に行ってもらうことで、カビを防ぎきれいに使い続けることができます。
エアコンのカビを予防する方法とは?
エアコンから漂う嫌なニオイの正体は、ほとんどがカビによるものです。内部でカビが発生すると、冷たい空気と一緒に胞子やカビ臭が室内にまき散らされ、アレルギーや喘息など健康面のトラブルを引き起こす恐れもあります。一度発生してしまうと、完全に取り除くのは難しく、専門業者によるクリーニングが必要になるケースも少なくありません。そのため、カビは「できてから対処する」よりも、「そもそも発生させないこと」が何よりも大切です。ここでは、家庭でできるエアコンのカビ予防策を、日常的なメンテナンスから使い方の工夫まで、幅広く解説していきます。今後のカビ対策の参考に、ぜひ参考にしてみてくださいね。
フィルターを定期的に掃除する
エアコンのフィルターは、部屋の空気を吸い込む際にホコリや花粉、皮脂などの汚れをキャッチする重要なパーツです。ですが、掃除を怠るとその汚れがどんどんたまり、カビにとっての栄養源となってしまいます。さらにフィルターが目詰まりを起こすと、空気の流れが悪くなり、内部の結露が蒸発しにくくなるため、湿気もこもりやすくなります。これらの要因が重なると、カビが繁殖するリスクは一気に高まります。フィルター掃除の目安は2週間に1回が理想ですが、使用頻度が少ない場合でも最低でも月1回は掃除するようにしましょう。掃除機でホコリを吸い取った後、水洗いでさらに汚れを落とし、しっかり乾燥させてから元に戻すことがポイントです。汚れがこびりついている場合は、ぬるま湯に中性洗剤を溶かして、しばらく浸け置きすると効果的です。
冷房使用後は送風運転で内部を乾燥させる
冷房運転や除湿運転を行うと、エアコン内部の熱交換器には結露が発生し、内部は高湿状態になります。この湿気をそのまま放置して電源を切ってしまうと、カビにとって最適な繁殖環境が長時間続くことになってしまいます。実は、エアコンのカビの多くは、こうした「運転終了後の湿気の残留」が原因で発生しているのです。そのため、冷房や除湿の使用後は、30分〜1時間ほど送風運転を行い、内部をしっかり乾燥させる習慣をつけることが非常に重要です。最近のエアコンには「内部クリーン」や「カビ抑制」機能が搭載されている機種もあり、自動で乾燥運転をしてくれる場合もあります。これらの機能は積極的に活用しましょう。乾燥を怠らず、常にエアコン内部をサラッとした状態に保つことで、カビの繁殖スピードを大幅に抑えることが可能になります。
室内の湿度管理を徹底する
カビの繁殖には「湿度」が大きく関係しています。特に湿度が70%を超えると、カビは急激に活動を始めるため、室内の湿度管理もエアコンのカビ予防において欠かせないポイントとなります。どんなにエアコン内部を乾燥させても、室内が常に高湿状態だと、再びエアコン内部も湿ってしまう恐れがあるのです。梅雨の時期や夏場は、湿度が非常に高くなりやすいため、除湿機やエアコンの除湿モードを上手に活用して、室内の湿度を50〜60%程度にキープするよう心がけましょう。また、観葉植物が多い、室内干しをしているなど、湿度が上がりやすい環境にある場合は、よりこまめな換気や除湿が必要になります。湿度計を部屋に置いておくことで、数値として把握できるため、日々の湿度管理がしやすくなります。「見える化」することで、意識が高まり、カビ対策もより確実なものになるでしょう。
長期間使用しない前に掃除と乾燥を行う
冷房シーズンが終わった秋口や、エアコンを使わない期間が続くときには、必ずその前にメンテナンスをしておきましょう。使い終わったままの状態で放置してしまうと、内部に残ったホコリや湿気が原因で、使用していない間にもカビがじわじわと繁殖してしまう恐れがあります。まずはフィルターや吹き出し口などを掃除し、その後、30分程度の送風運転を行って内部の水分をしっかり飛ばすことが基本です。さらに、できれば冷房の最終使用後には一度、専門業者による内部クリーニングを依頼して、内部の奥にたまった汚れやカビをリセットしておくと安心です。こうして使用前・使用後の「ケア」を徹底することで、次のシーズンも清潔な状態でエアコンを使い始めることができ、カビ臭やトラブルを未然に防ぐことができます。
吹き出し口やルーバーの汚れをこまめに拭き取る
エアコンの吹き出し口やルーバー(風向きを調整する羽の部分)は、カビの胞子が空気の流れに乗って最初に付着しやすい場所です。また、冷房時にはこの部分にも結露が発生しやすく、湿気と汚れが重なることで、カビが発生しやすい環境が生まれます。週に1回を目安に、柔らかい布やキッチンペーパーに中性洗剤を含ませて、優しく拭き掃除をするようにしましょう。アルコールスプレーを使って除菌を兼ねると、よりカビの発生を防ぐ効果が高まります。定期的に掃除をしておくことで、カビだけでなくホコリや臭いの蓄積も防げます。
定期的にプロのエアコンクリーニングを利用する
どれだけこまめに掃除をしていても、エアコン内部の奥深くには手の届かない汚れや湿気がどうしても残ってしまいます。特に、熱交換器や送風ファンといったカビの温床になりやすい部分は、一般の家庭用の掃除道具では完全にキレイにするのは難しいものです。そのため、1〜2年に1回を目安に、プロのエアコンクリーニングを依頼するのがおすすめです。専門業者であれば、エアコンを分解して細部まで徹底洗浄してくれるため、内部に潜むカビやバクテリア、臭いの元までしっかり取り除いてくれます。定期的にプロの手を入れることで、エアコンの性能維持や電気代の節約にもつながり、結果的に快適で清潔な空間を維持できるようになります。
まとめ
弊社では水回りトラブルの無料お見積り、修理を行っておりますのでお困りの際は是非ご連絡ください。関東エリア・東北エリア・東海エリア・関西エリアの各拠点にスタッフが待機しておりますので、お問い合わせから最短20分で駆けつけます。不安なことがありましたら是非ご連絡ください。